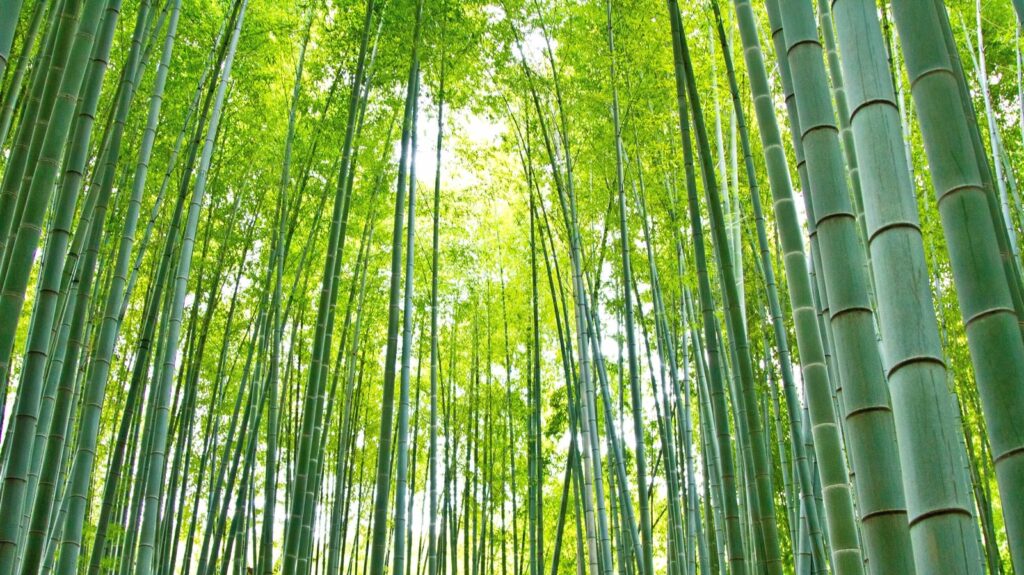令和5年12月6日(水)NHK テレビ「美の壺」を観ました。
番組の中に、子育てに通じる言葉があったので紹介します。
京都 地蔵院(竹の寺)
途中視聴だったため観終わってから、
「美の壺 竹林 京都」とスマホ検索したら、
「まっすぐ清らか 竹」と番組タイトルが出ました。
「竹の寺」と呼ばれる京都のお寺だそうです。
「京都 竹の寺」と調べると「地蔵院」ということがわかりました。
とんちで有名な一休さん生誕の地とのことです。
一休宗純禅師(一休さん)は、地蔵院・寺領地内で生まれ、幼少期をお母さんと一緒にここで過ごし、その後、6歳で安国寺に入門されました。
テレビアニメ「一休さん」が懐かしいですね。
南北朝時代の臨済宗の禅僧・夢窓疎石が開山した寺院で、南北朝時代の管領・細川頼之が地蔵院を創建したとのことです。
番組でお話をされていたのは住職さん。優しそうな方です。
美しい竹林にするためには、毎日の手入れが必要であり、訪れる方のために、それはそれは大変な作業を毎日されているとのことでした。
竹林はテレビの画面越しでも息をのむ美しさでした。
「この美しさは人が手入れをした人工美である」
と、誇らしそうにおっしゃっていました。
手をかけるほど 輝く
竹は毎日手入れをすることで、まっすぐに美しく育つのです。
頭上から降り注ぐ太陽の光で竹の緑が輝きます。
竹は密集しないように、等間隔に広く離れているようです。
しかし、日光が当たりすぎても竹の成長に良くないため、間隔は離れすぎてもいけないとのこと。
竹の密度は高すぎず低すぎず、ちょうどを保つ。保ち続ける。
それが手入れをしているということです。
竹は、地下茎によって繁殖する生命力の強い植物です。
成長と繁殖のスピードが速いため、人が手を入れないと竹やぶになってしまいます。
昔は、伐採した竹は生活に役立つ資材として重宝されていました。
時代は変わり竹を切らなくなって、放置されたままの竹が竹やぶとなって散在しています。
子どもも放置をすると荒れますよね?
*ポイント*
「手入れさえきちんとすれば、あとは竹自身の力でぐんぐんまっすぐに成長していきます」
「手入れをしないで放置すると、荒れます」
おわりに
人が手をかけるというのは簡単なことではありません。重労働です。
しかし、大変なことを継続すると、まるでご褒美のように素敵な景観をみせてくれるのです。
子育ても同じです。
子育てのヒントは身の回りにたくさんあるのかもしれないですね。
また何か具体的なヒントを見つけたらブログに書きますね。
*まとめ*
①美しい竹林は人の手入れによって成り立つ人工美である
②子どもも手をかけて輝かせましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。