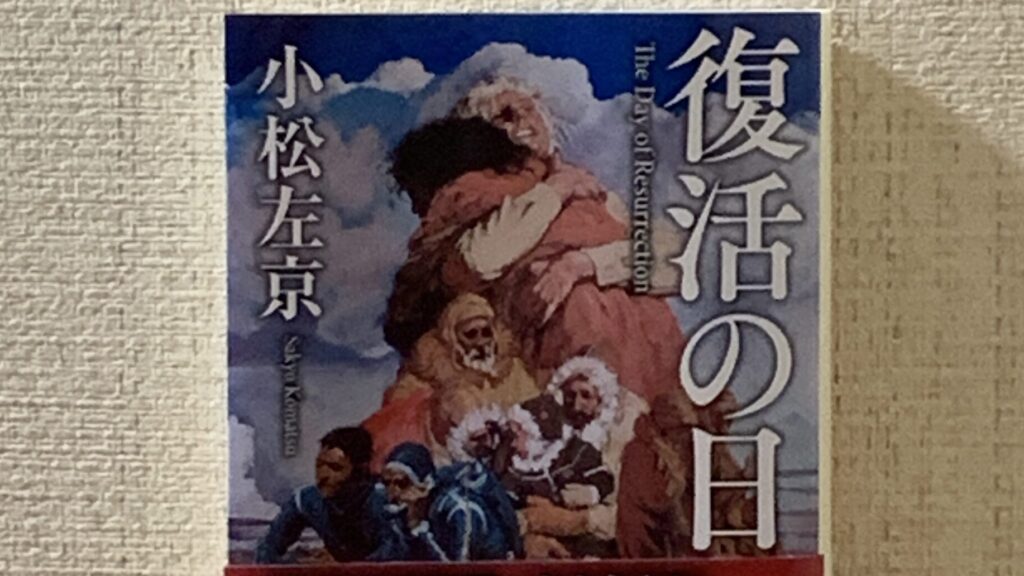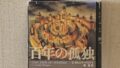昭和のSFの大家・小松左京先生。
「日本沈没」にならび有名な作品「復活の日」。
コロナを予言したかのようなこの本をコロナ禍に買い求めた人は多かったようです。
人々は、行く末の未来を知りたかったのか。
非常時の所作や心構えを知りたかったのか。
覚悟を決めたかったのか。
未曽有の出来事の中、この本はバイブルのように読まれたに違いありません。
感染症のリアル
小説「復活の日」。
前々から読みたい本ではありましたが、買ったのはコロナウィルス出現から数年後。
読み終えたのは、つい最近のことです。
今まではずっと怖くて読めなかった💦
優れたエンターテイメント作品として、娯楽作品として読めるようになったのが最近なのです。
令和6年になり、コロナ禍の記憶が薄れつつあります。
手指のアルコール消毒をしたりしなかったり、密になる場所へ出かけることも増えました。
しかし、依然としてコロナウィルスは残っているため、我が家では手洗い・消毒・マスク・検温生活を今も続けています。
もはや、出現してしまったコロナウィルスは変異し続けて消えることはないのでしょうから。
コロナ禍の読書
復活の日
小説「復活の日」。
まるでコロナを予言したかのような、未知のウィルスに侵された世界がえがかれています。
コロナの始まりが2019年12月。令和元年。
「復活の日」「日本沈没」が再版、発行されたのが令和2年です。
私がこの3冊を購入したのは令和3~4年頃。
「復活の日」 角川文庫
昭和50年10月30日 初版発行
平成30年8月25日 改版初版発行
令和2年9月10日 改版10版発行
(*昭和39年8月に描きおろし作品として早川書房から出版されています。)
日本沈没
「日本沈没(上)」 光文社 ➡ 角川文庫
昭和48年3月 カッパ・ノベルス(光文社)刊行
城西国際大学出版会版「小松左京全集 完全版5 日本沈没」(平成23年2月)を底本とし、角川文庫化
令和2年4月25日 初版発行
令和3年10月15日 9版発行
「日本沈没(下)」 光文社 ➡ 角川文庫
昭和48年3月 カッパ・ノベルス(光文社)刊行
城西国際大学出版会版「小松左京全集 完全版5 日本沈没」(平成23年2月)を底本とし、角川文庫化
令和2年4月25日 初版発行
令和3年11月20日 11版発行
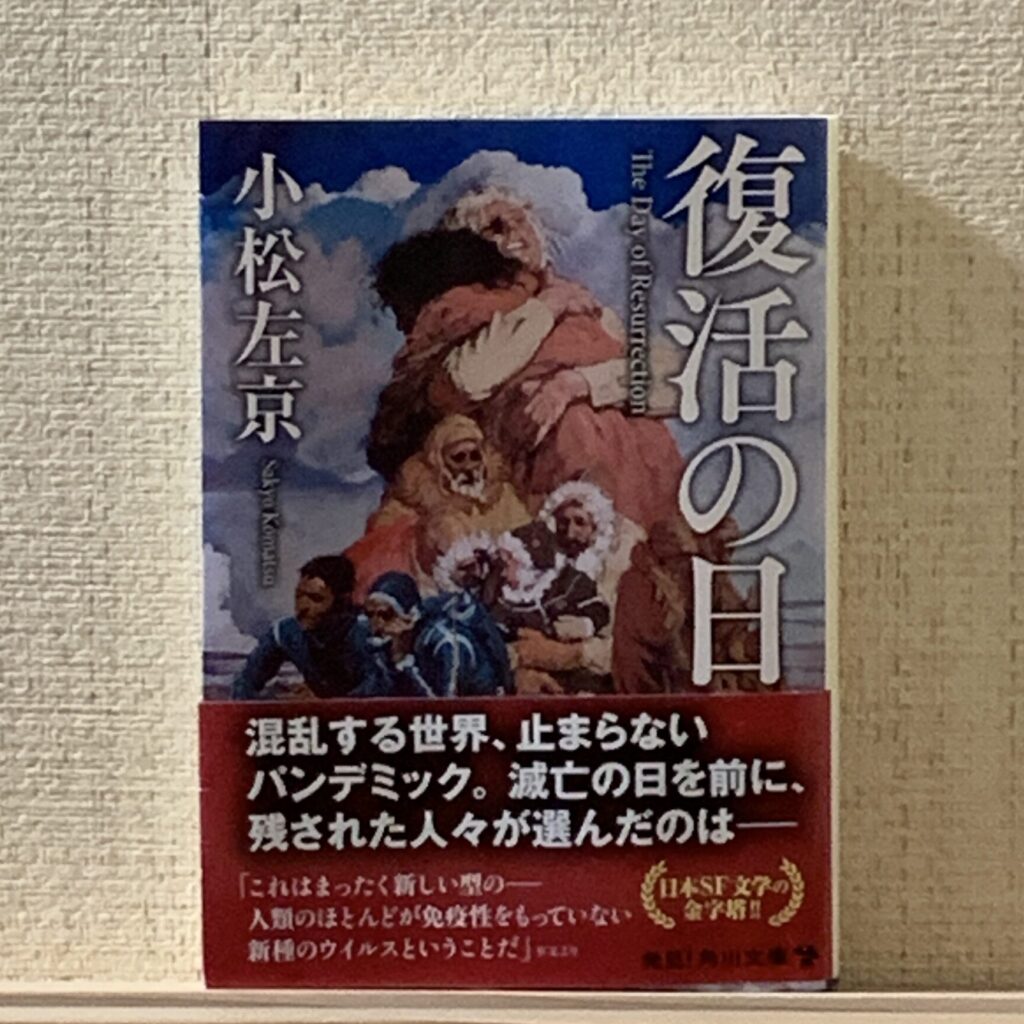
コロナ禍、多くの人がこれらの本を買ったことがわかります。
他人との接触禁止により、幸か不幸か読書時間はつくれましたね。
コロナの真っただ中に読んだ人は勇気があるなと感じます。
「日本沈没」も売れています。私も買いました。
「日本沈没」を読むのはこれからです。
ありえないと思いたいから娯楽作品として読みたいのかもしれません。
読み終えて、予防策があるのなら実行したいと思いますし、すべきですね。
学びとして
「復活の日」はインターネットが発達していないころの話なので、テレビ・ラジオ・無電気・電話機を使用しています。
小説の内容は、たいへんリアルです。
これは作者の想像であり、妄想ではありません。
国際情勢を分析すると、このような話が無理なくできあがってしまうのだと感じます。
小松左京先生は危惧していたと思います。
本を買って読まれた人は、後世への責任感が強い人なのかもしれません。
人間の未来を守りたいと考えてくれたのかもしれません。
今を生きる私たちが世の中を良くしていかないと、人類は滅ぶかもしれないからです。
頭の良い人が書いた本から学ばなければなりません。
予防・協力・理解という言葉が私には浮かびました。
ワクチンの是非
日本製がなかった
私の記憶では、日本はワクチン開発に手薄だったと言われていたと思います。
コロナワクチンは、日本では以下の三つが接種されました。
・ファイザー製(mRNAワクチン)は、米ファイザー社とドイツのバイオ企業ビオンテック社の共同開発。
・モデルナ製(mRNAワクチン)は、米モデルナ社。
・アストラゼネカ製(ウイルスベクターワクチン)は、英アストラゼネカ社。
製造方法、接種方法、効果など違いはありますが、ほぼ同時期にコロナ禍で実用化されました。
すべて外国製。国産はありませんでした。
日本に経済力がなかったらワクチンを打てなかったかもしれません。
(日本の科学者・医学者・企業らが開発に協力していたおかげで、日本にはワクチンがたくさん入ったと聞きました。)
小説「復活の日」を読んでいたならば、日本もずっと前からワクチン開発に着手できていたはずです。
真摯に開発に取り組めていたはずです。
副反応
副反応はワクチン接種の心配の要素です。
私自身、副反応を心配して息子に心臓の検査を受けさせています。幸いワクチンの副反応ではありませんでした。
人口の8割以上がワクチン接種をして免疫力をつけないと全体効果が望めないため、なかば強制的に接種はおこなわれました。
しかし、大切な命を落とされる人もいました。
アレルギー体質の人はいらっしゃいます。
私が聞いた話では、ある施設入所の高齢者数名はワクチン接種を断ったそうです。
外部接触が制限されていたのもありますが、個人の意思が尊重されました。
選択肢を増やすことにより、いかに人類が全滅せずに済むか、わずかな人数でも生き残れるか、可能性は見出せます。
多様性というのはそういうもので、どんな価値観を持った人が生き残れるのかは運としか言えないのかもしれませんが、価値観が違い選択肢が違うことで人類が全滅せずに済むのです。
何が正しい選択なのか、わかりません。
おわりに
コロナがだいぶ落ち着き、コロナ前と変わらぬ生活ができるようになりました。
これは、みんなの努力の賜物です。
つらいこと、悲しいことを経験しました。
「喉元を過ぎれば熱さを忘れる」にならないようにしたいものです。
「復活の日」を読みコロナ禍を振り返り、感染症の怖さ・ワクチンという救い・国家間の平和協定などを考えさせられました。
人間の優しさや勇気に心を打たれました。一部の人間の愚かさには腹が立ちました。
表現に困りますが誤解を恐れずに言うと、とてもおもしろく読めました。改めて、偉大な作家・小松左京先生に敬意を表します。
令和2年版は小松左京先生の「初版あとがき」が掲載されていました。人類への憂いとともに人類への信頼が伝わってきました。
小松実盛(さねもり)さんの解説には様々なエピソードが盛り込まれて楽しく読めました。
忘れてはならないのは「復活の日」をフィクションで終わらせてはもったいないということです。
最後までお読みいただきありがとうございました。